今治店!!知っていますか?ナンバープレートの歴史!!
2021.03.28
皆さまこんにちは(^^)/
愛媛トヨペット 今治店 店頭スタッフの久徳です♪
3月に入り、桜の花がちらほら咲き始め、だんだん春らしくなってきましたね(*´ω`*)🌸
皆さまいかがお過ごしでしょうか??
季節の変わり目ですので、体調など崩されないように気を付けてくださいね😌
さて、本題に入る前にこちらの画像をご覧ください!

皆さんのお車に付いているナンバープレートと比べてみてください😲
この写真のナンバープレートは、お客様が長年大切に乗られていたお車に付いていました✨
『愛媛』の字体や、その横の分類番号が2桁であることが歴史を感じさせますよね!
このナンバープレートはどれぐらい前のものなのか、気になったので調べてみました!!
昔のナンバープレートの入手が難しかったので、手作りナンバープレートの写真とともに説明していきます🚙笑
明治時代
日本でナンバープレートを装着し始めたのは明治時代といわれています。
当時は信号や交通標識などの交通を整備するものが整っておらず、自動車の事故が多発していたそうです。
そのため、誰が所有している自動車なのかを識別するためにナンバープレートの装着が義務付けられました(`・ω・´)
1951年(昭和26年)
「道路運送車両法」によって自動車の登録制度が確立します。
そのころのナンバープレートには、府県名の頭文字、分類番号などが横一列に表示されていました!
東京都だけは地名の表記は省略されました。
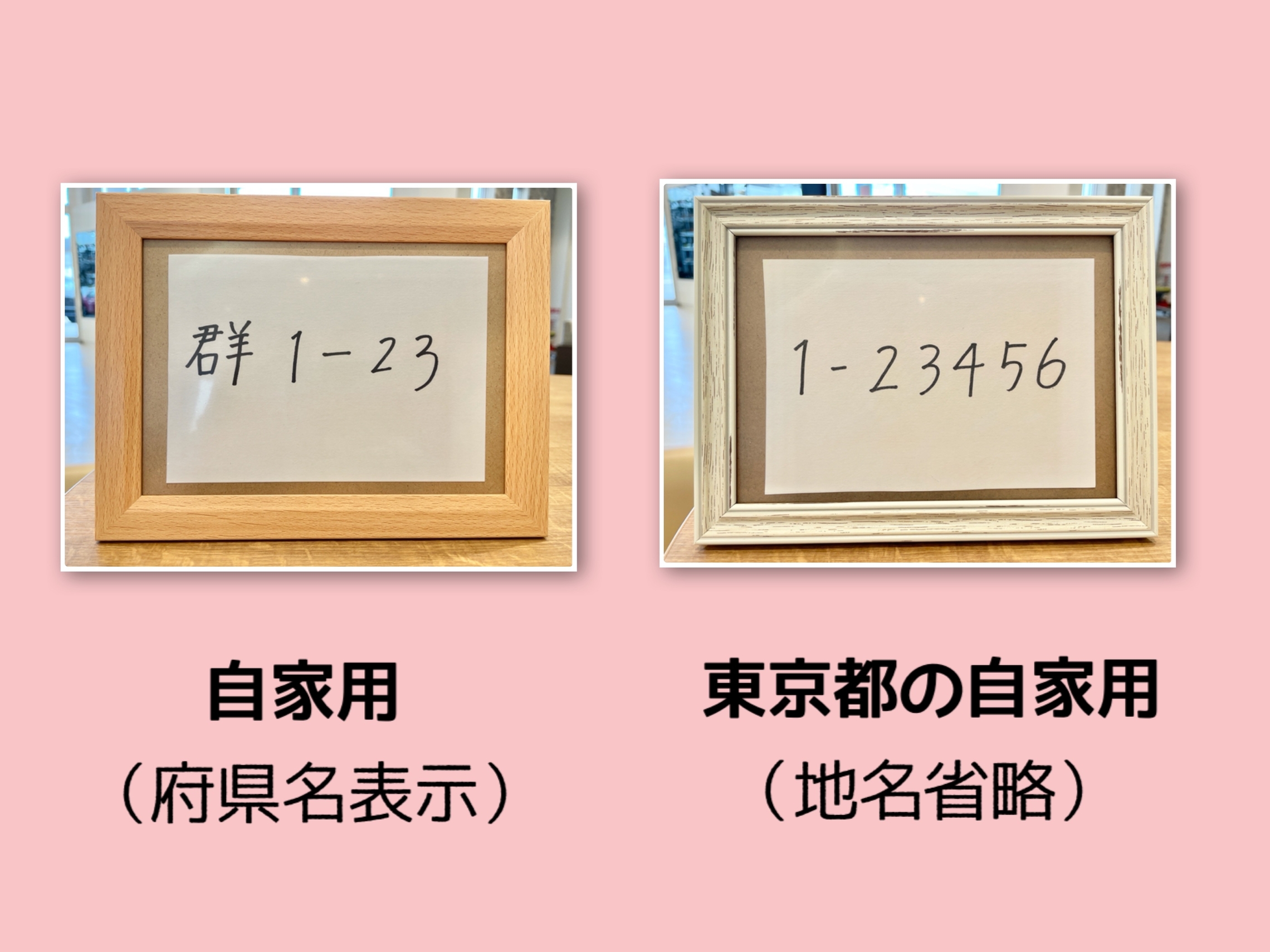
1955年(昭和30年)
普通・小型自動車と軽自動車のナンバープレートに「ひらがな」が加えられ、上下二段表示に変わります。

1962年(昭和37年)
普通・小型自動車と軽自動車どちらも事業用を緑地のナンバープレートに変更されます。
このころ、大型トラックやバス用の大型ナンバープレートが登場します。
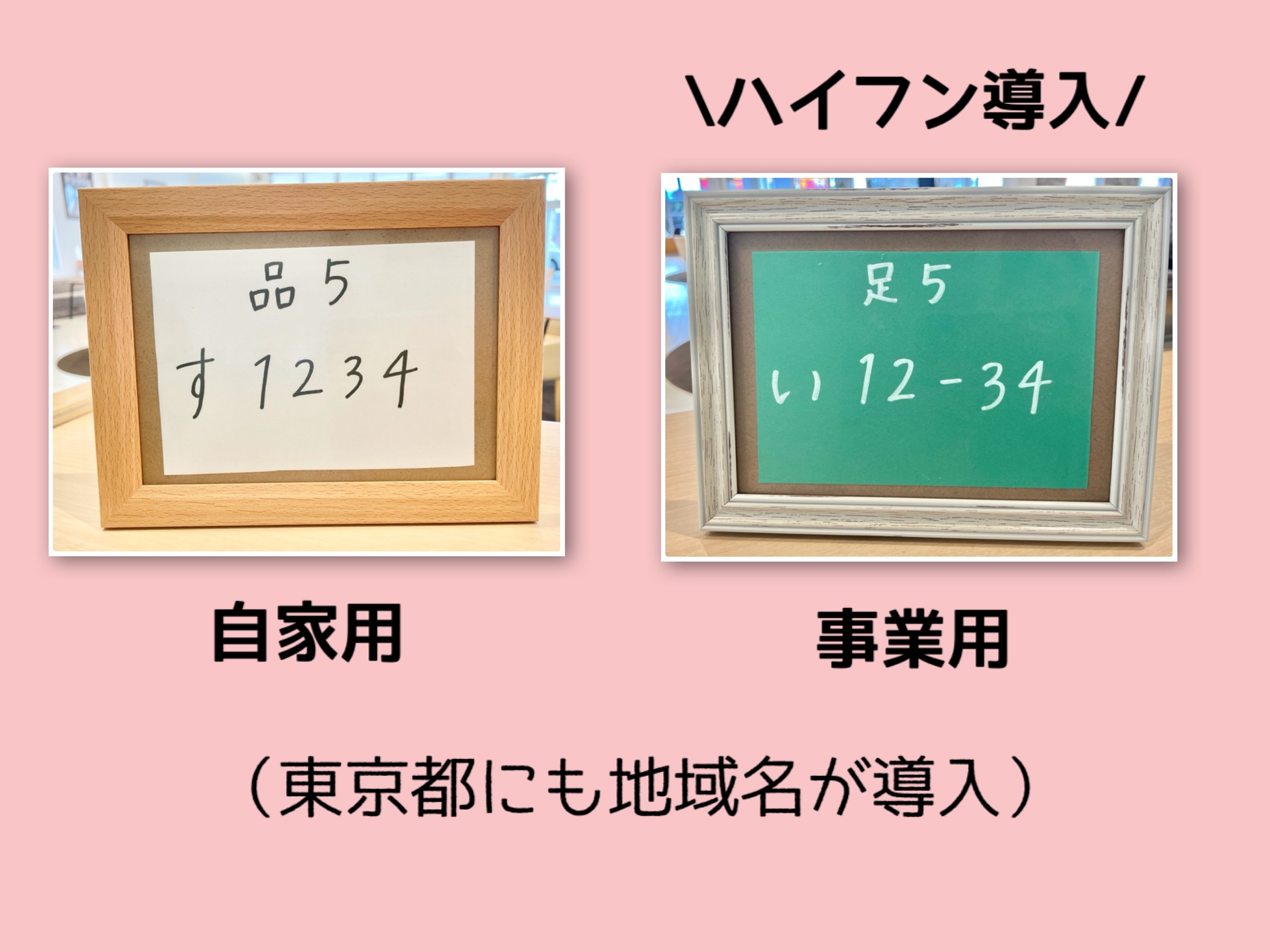
1964年(昭和39年)
普通・小型自動車と軽自動車とも地域名が頭文字のみからフルネーム表示に順次移行していきます。
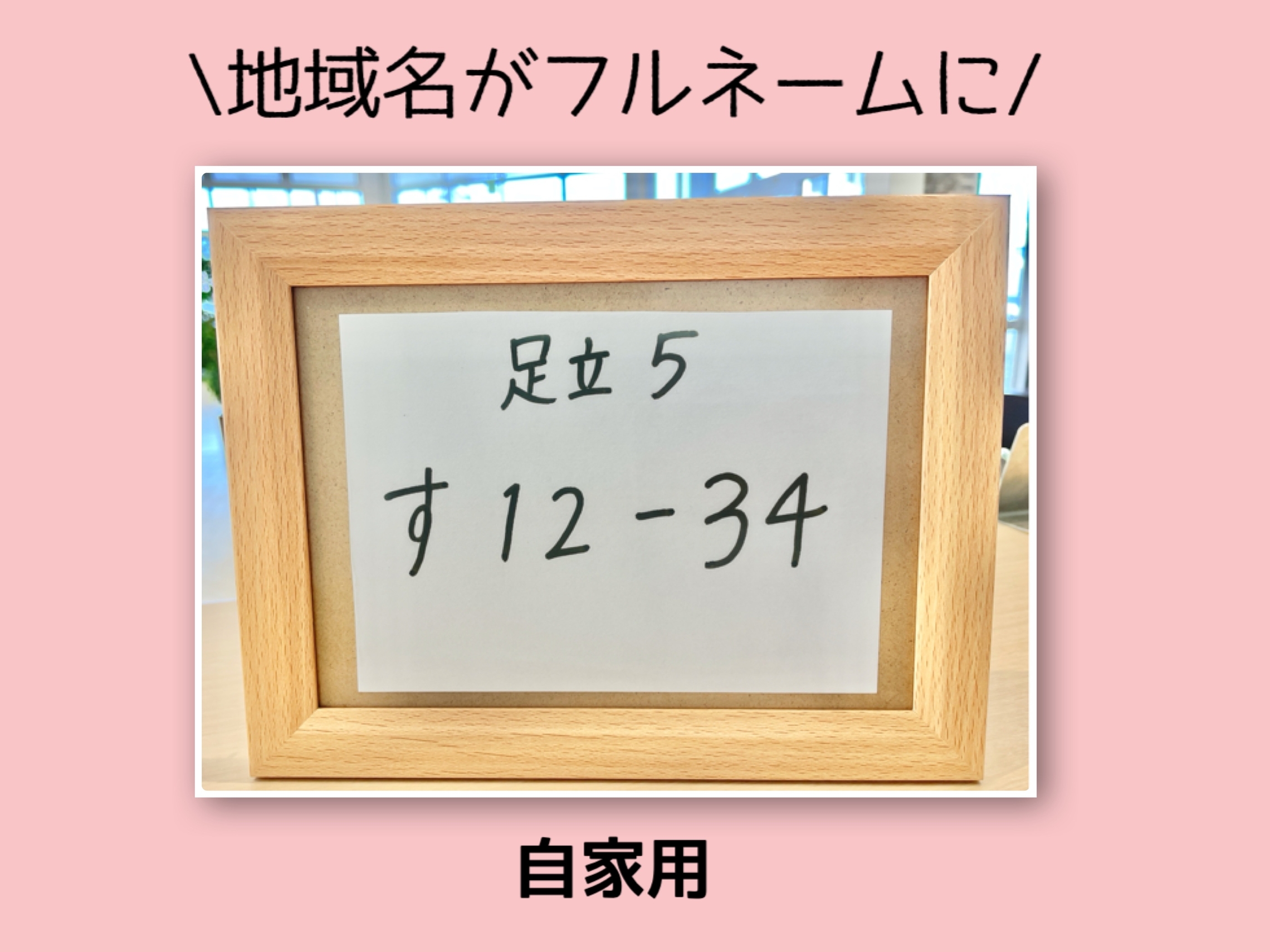
1967年(昭和42年)
普通・小型自動車の分類番号が二桁になりました。
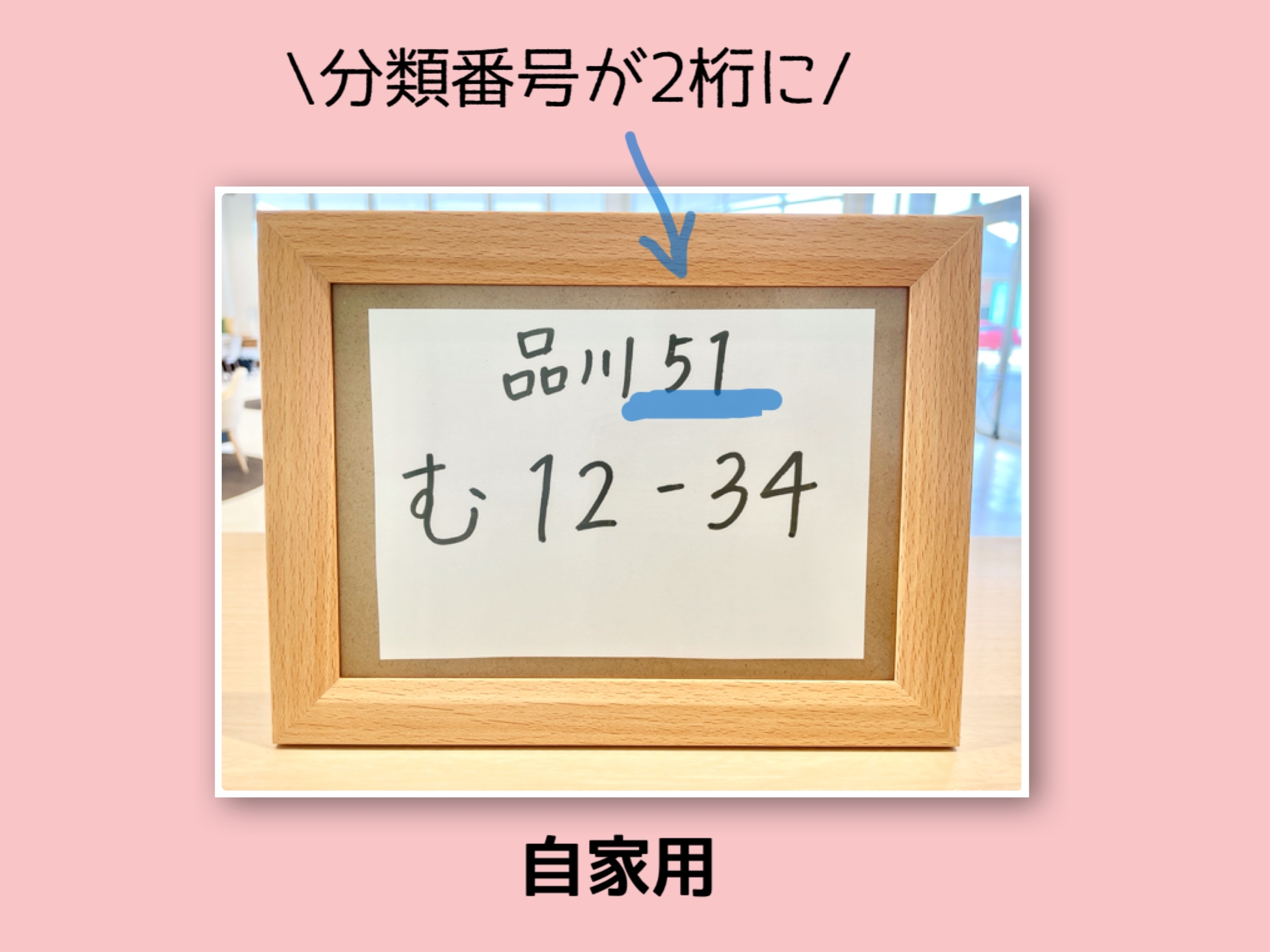
1975年(昭和50年)
軽自動車のナンバープレートの大きさと表示方法が普通・小型自動車と同じになりました。
軽自動車で自家用車が黄色地、事業用が黒地になったのはこの頃です。
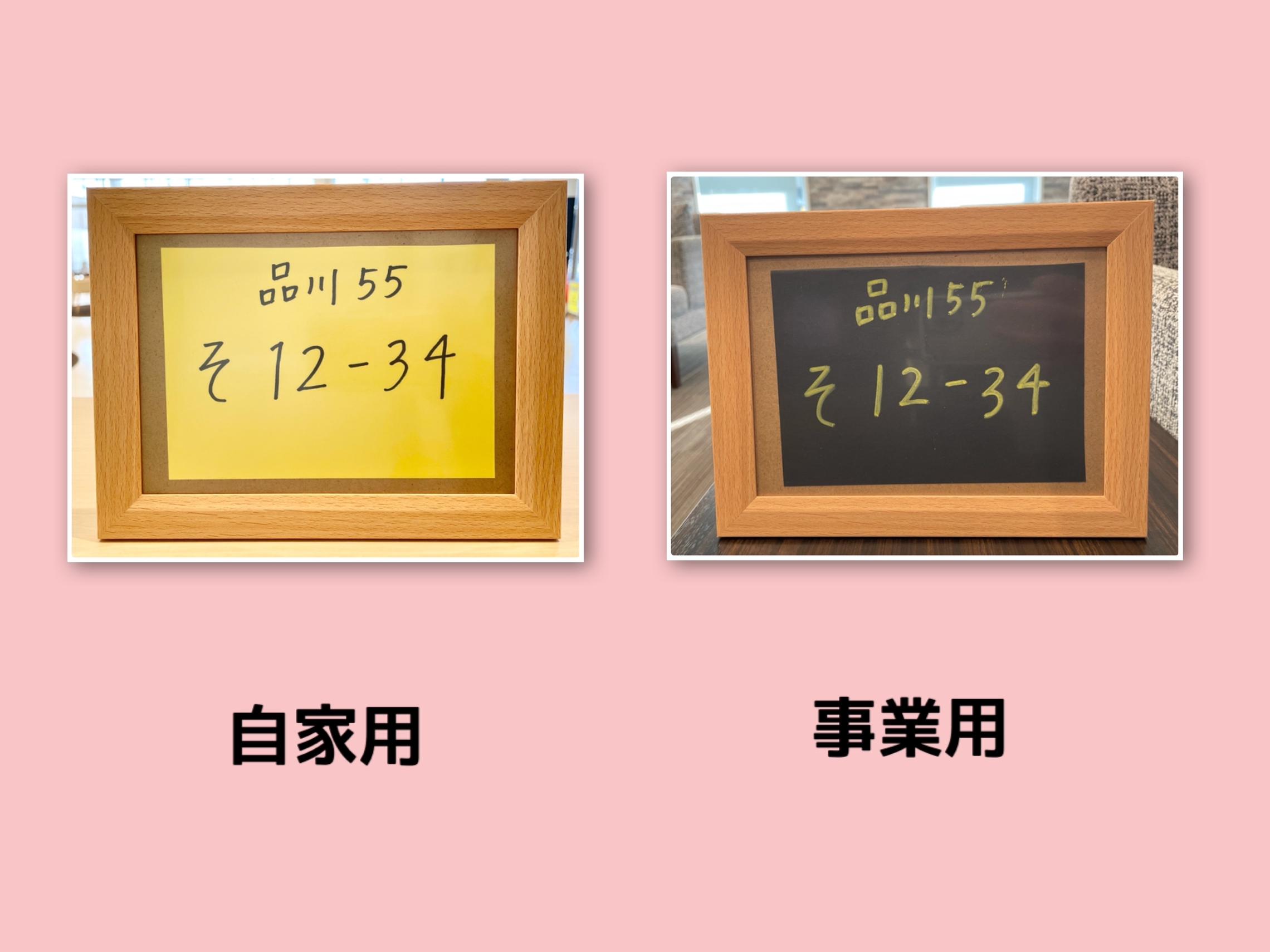
1999年(平成11年)
普通・小型自動車の分類番号が三桁になりました。
全国で希望番号制がスタートします。
(平成10年に先行で開始された地域もあります)
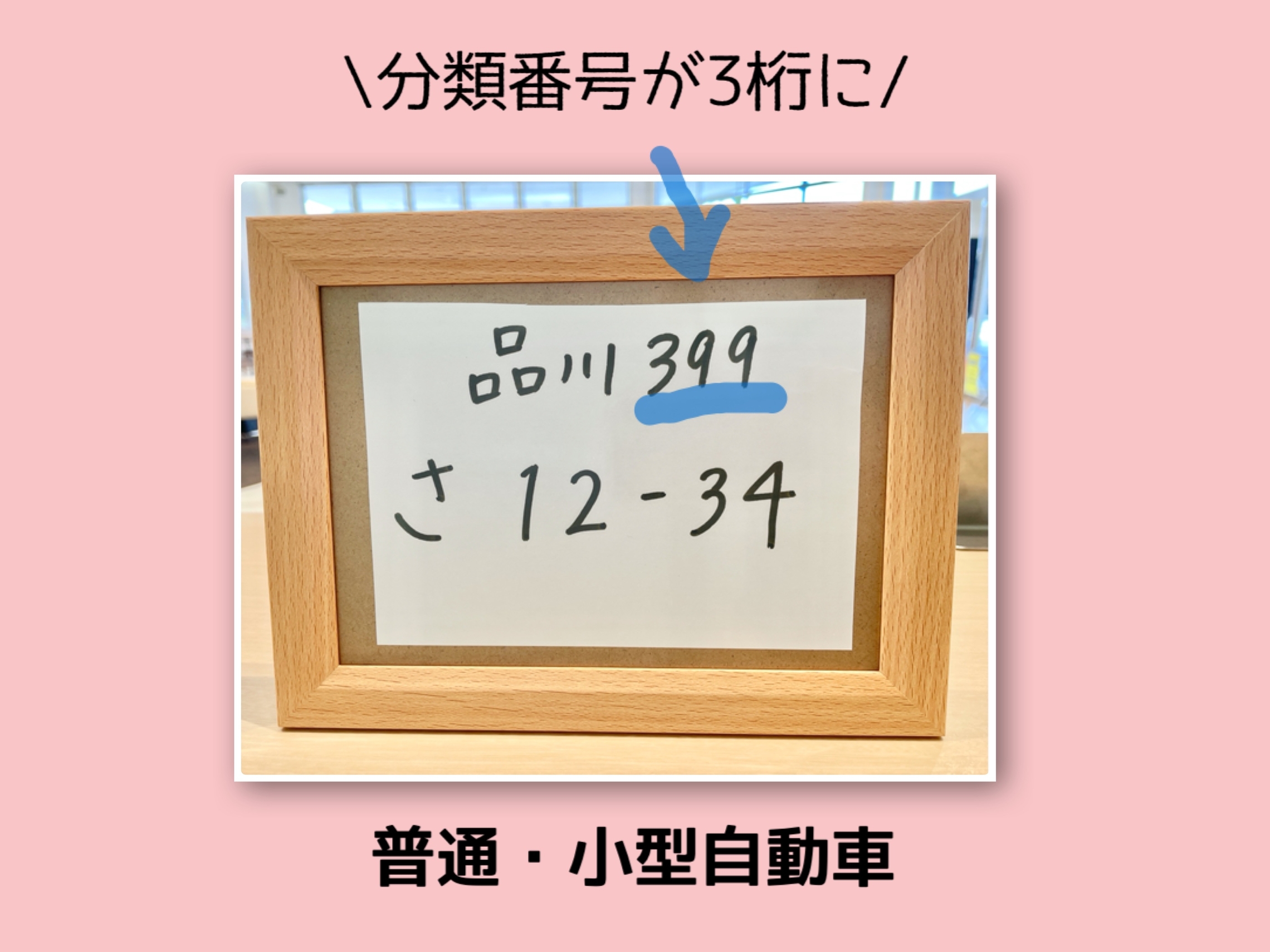
2005年(平成17年)
軽自動車も分類番号が三桁になり、希望番号制もスタートしました。
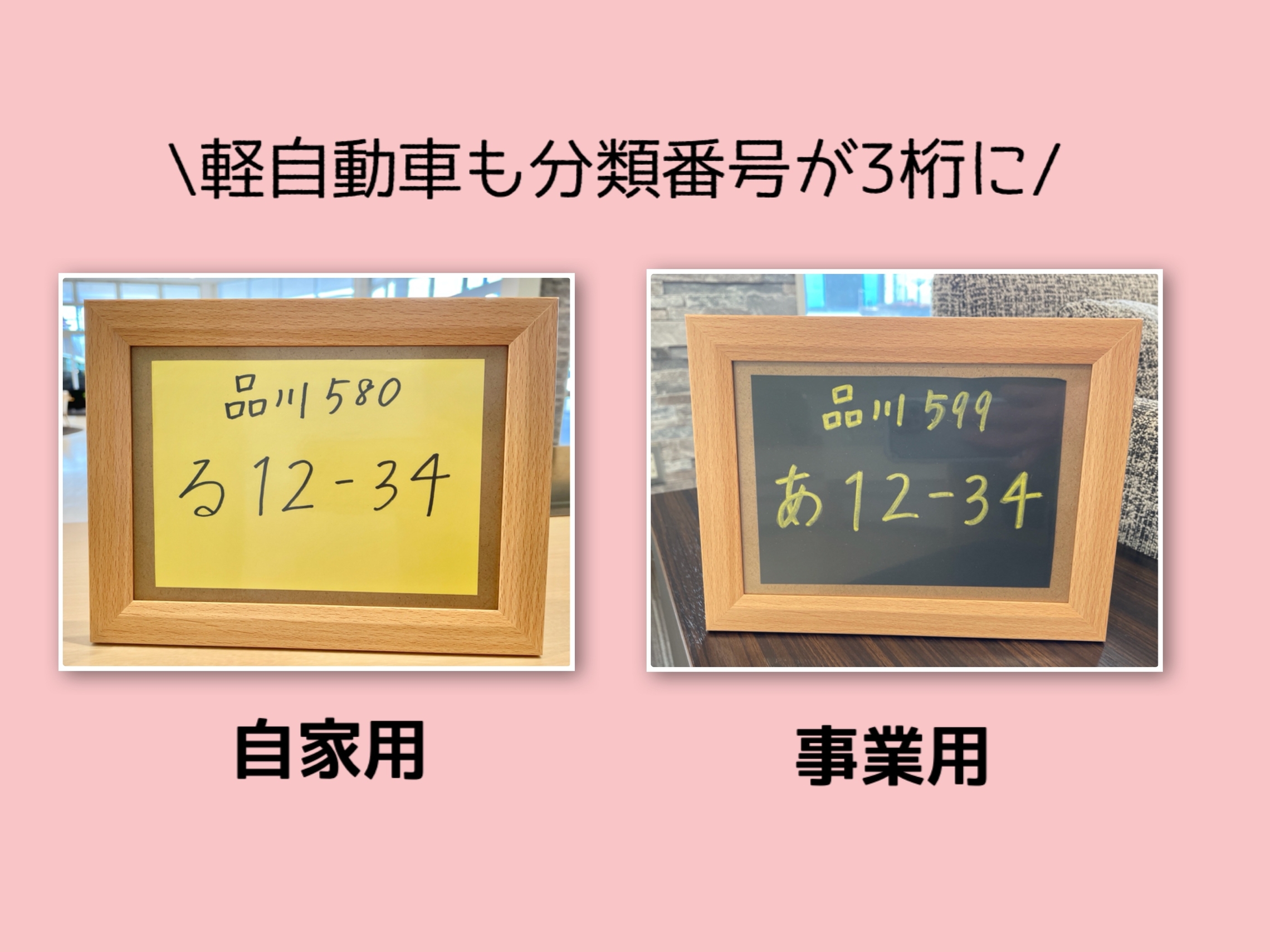
2006年(平成18年)
ご当地ナンバーが導入されました!
平成20年までに19地域20か所で交付開始となりました。
ご当地ナンバーの図柄はこちらから🍊(リンク:国土交通省ホームページ)
いかがでしたか??
ナンバープレートって色も表記も少しずつ変化して今の形になったんですね!💡
意外と歴史が深くて驚きました(; ・`д・´)
これから、すれ違う車のナンバープレートを見てみるのも楽しそうだなと思いました(^^)
皆さんもぜひ注目して見てみてはいかがでしょうか🌟
ナンバープレートを記念保存する方法をご紹介した記事はコチラ↓↓
今治店!!ナンバープレートの記念保存って??
次回のブログは、4月・5月の限定ドリンクについてお知らせしますので、楽しみにしていてくださいね🌸

愛媛トヨペット 今治店 店頭スタッフの久徳です♪
3月に入り、桜の花がちらほら咲き始め、だんだん春らしくなってきましたね(*´ω`*)🌸
皆さまいかがお過ごしでしょうか??
季節の変わり目ですので、体調など崩されないように気を付けてくださいね😌
さて、本題に入る前にこちらの画像をご覧ください!

皆さんのお車に付いているナンバープレートと比べてみてください😲
この写真のナンバープレートは、お客様が長年大切に乗られていたお車に付いていました✨
『愛媛』の字体や、その横の分類番号が2桁であることが歴史を感じさせますよね!
このナンバープレートはどれぐらい前のものなのか、気になったので調べてみました!!
昔のナンバープレートの入手が難しかったので、手作りナンバープレートの写真とともに説明していきます🚙笑
明治時代
日本でナンバープレートを装着し始めたのは明治時代といわれています。
当時は信号や交通標識などの交通を整備するものが整っておらず、自動車の事故が多発していたそうです。
そのため、誰が所有している自動車なのかを識別するためにナンバープレートの装着が義務付けられました(`・ω・´)
1951年(昭和26年)
「道路運送車両法」によって自動車の登録制度が確立します。
そのころのナンバープレートには、府県名の頭文字、分類番号などが横一列に表示されていました!
東京都だけは地名の表記は省略されました。
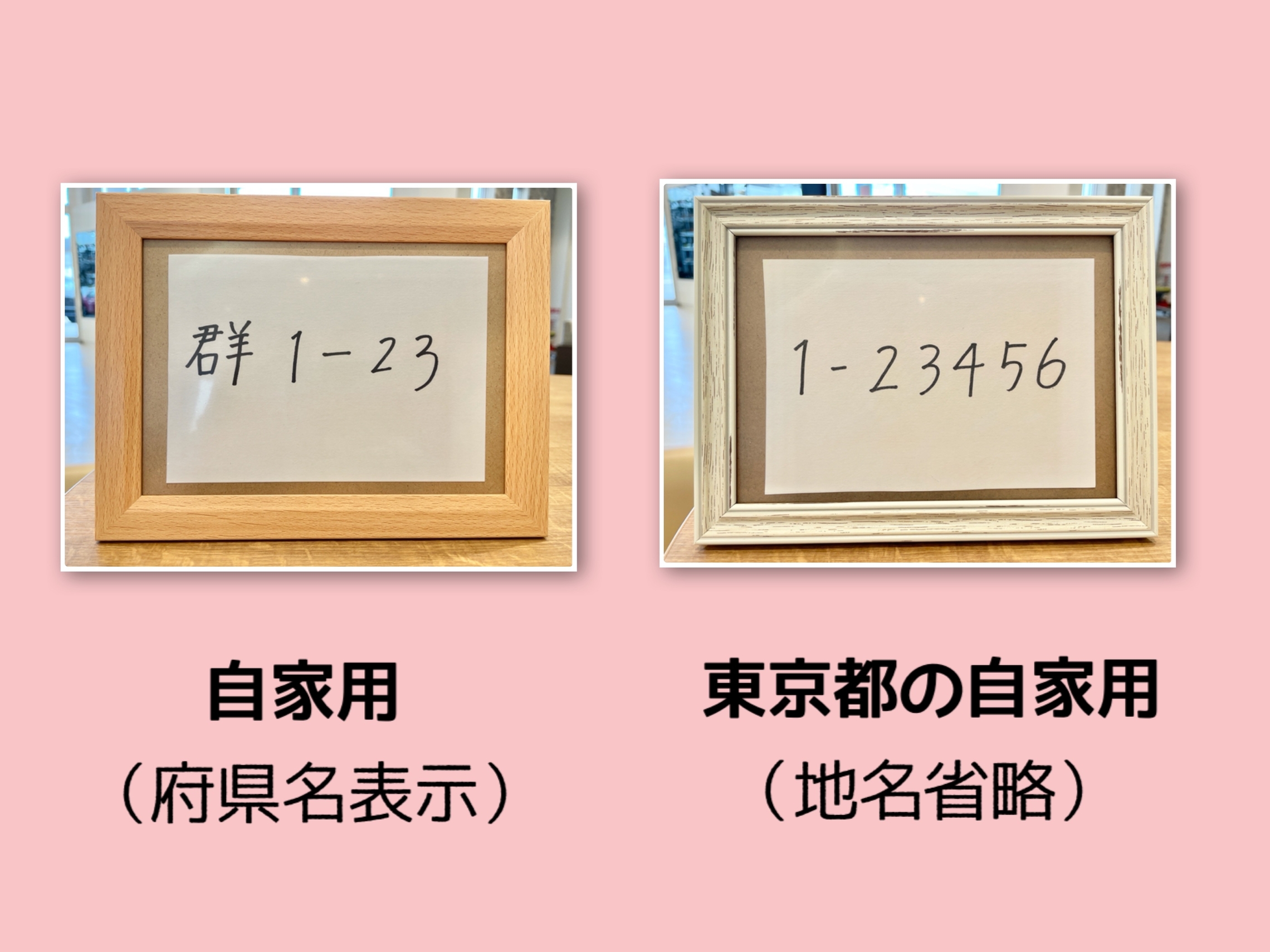
1955年(昭和30年)
普通・小型自動車と軽自動車のナンバープレートに「ひらがな」が加えられ、上下二段表示に変わります。

1962年(昭和37年)
普通・小型自動車と軽自動車どちらも事業用を緑地のナンバープレートに変更されます。
このころ、大型トラックやバス用の大型ナンバープレートが登場します。
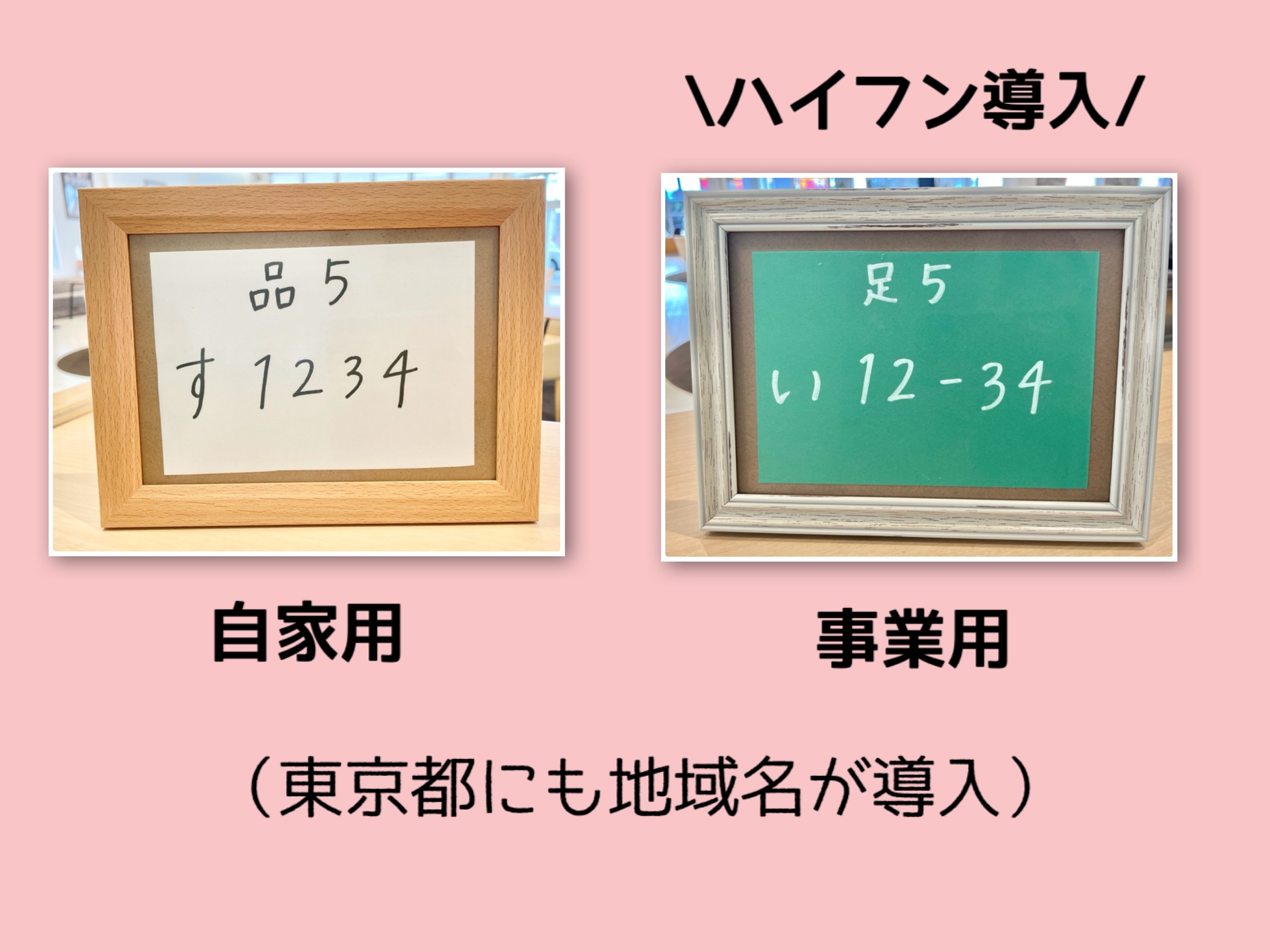
1964年(昭和39年)
普通・小型自動車と軽自動車とも地域名が頭文字のみからフルネーム表示に順次移行していきます。
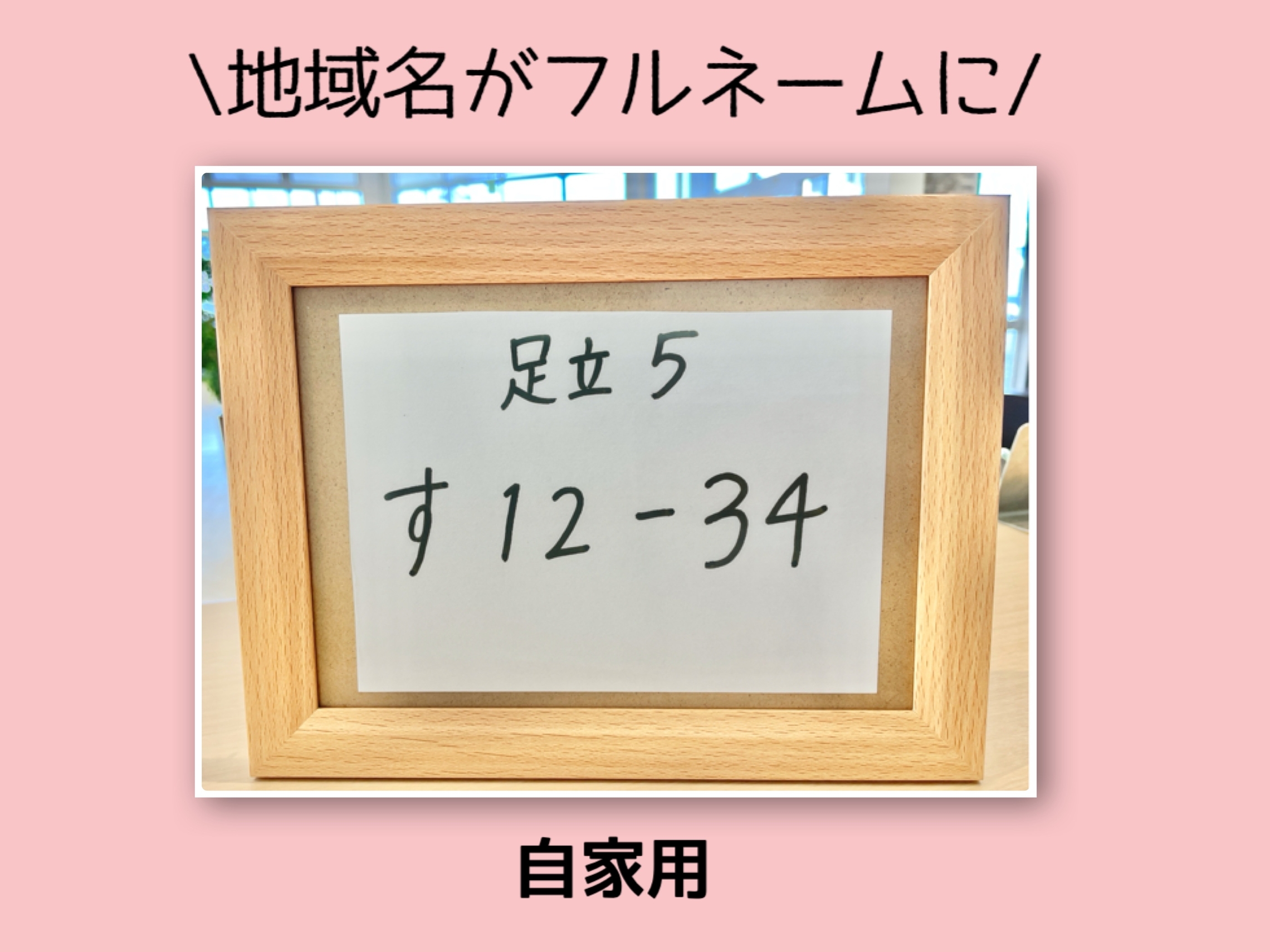
1967年(昭和42年)
普通・小型自動車の分類番号が二桁になりました。
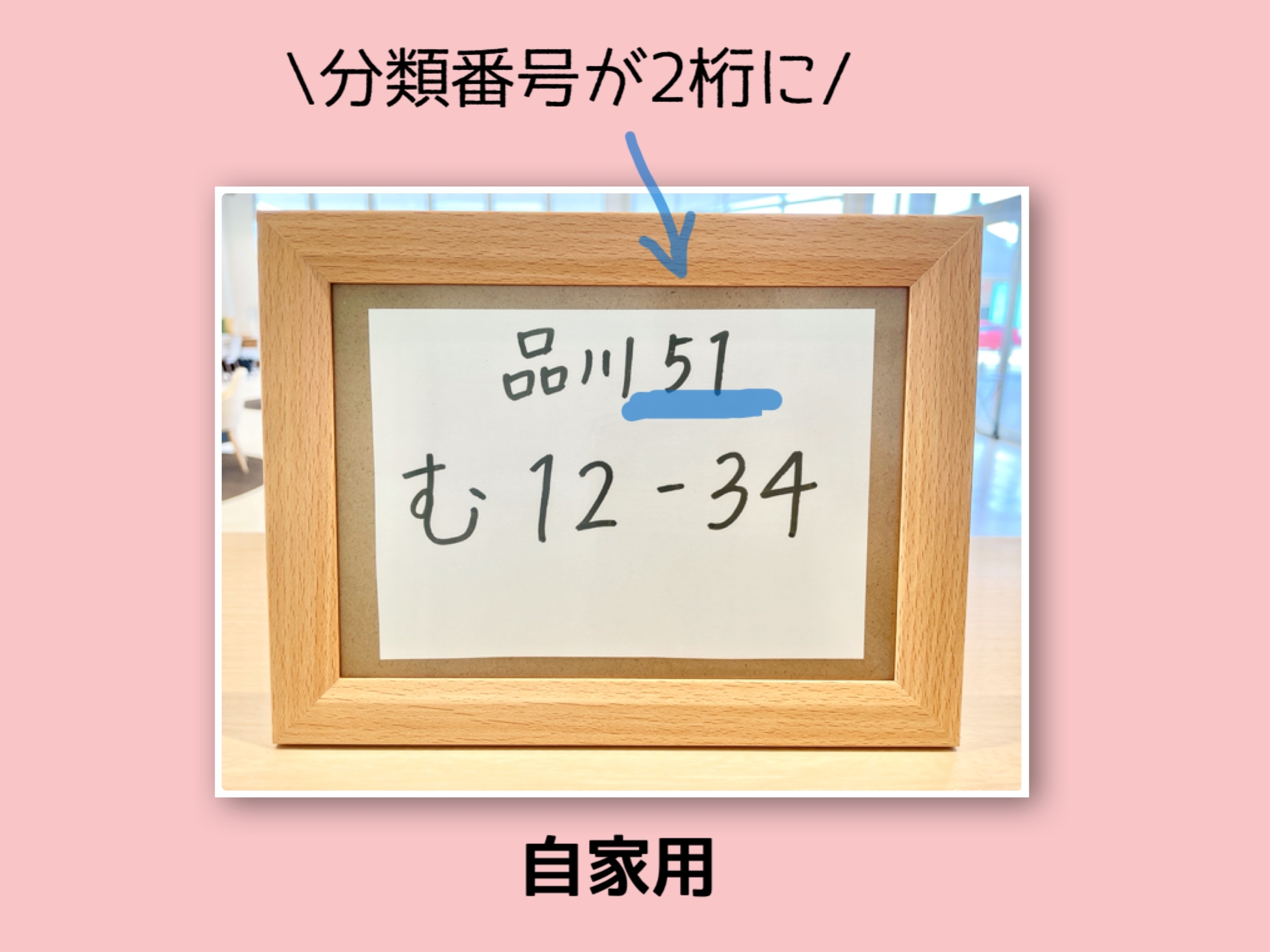
1975年(昭和50年)
軽自動車のナンバープレートの大きさと表示方法が普通・小型自動車と同じになりました。
軽自動車で自家用車が黄色地、事業用が黒地になったのはこの頃です。
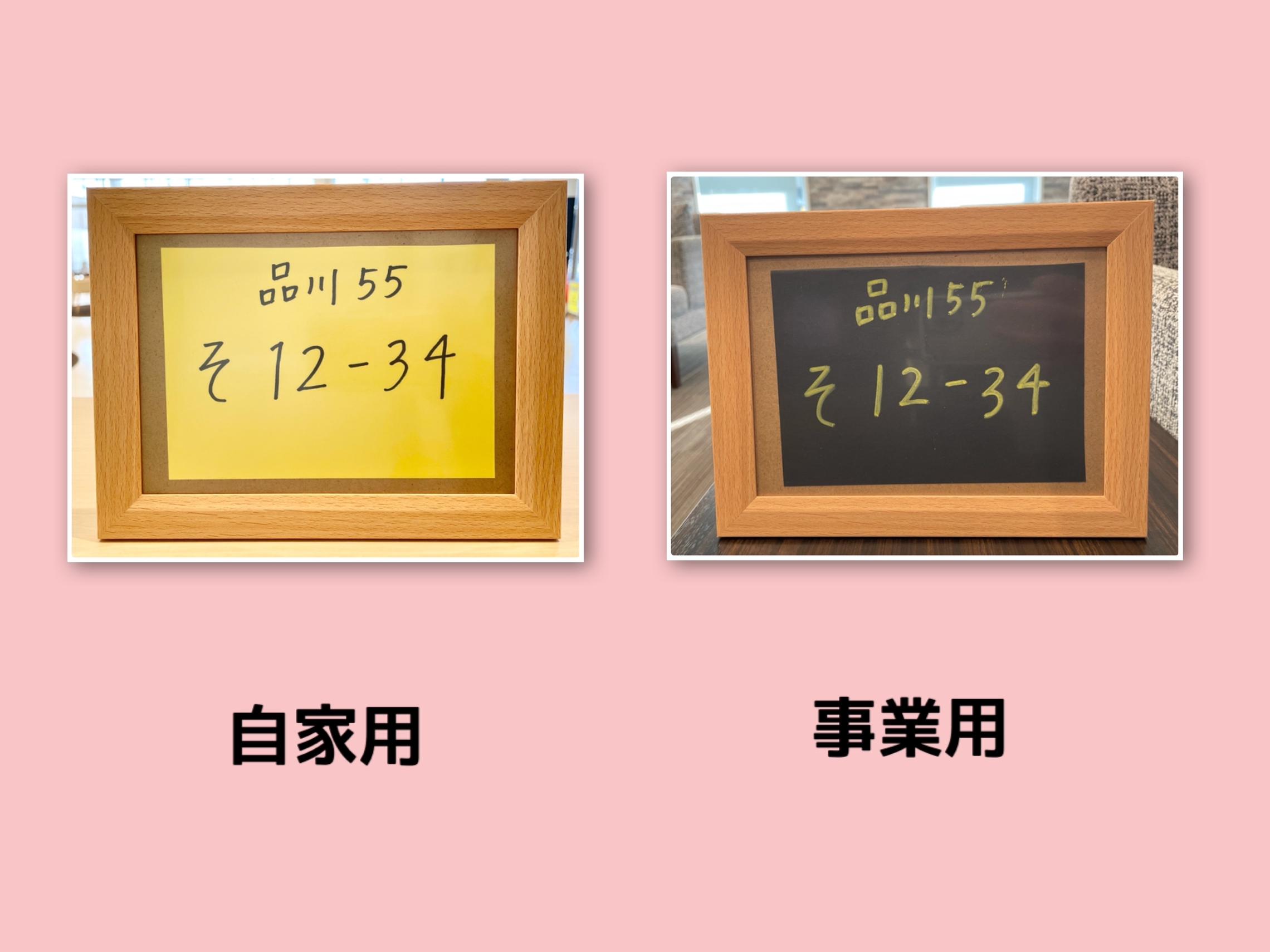
1999年(平成11年)
普通・小型自動車の分類番号が三桁になりました。
全国で希望番号制がスタートします。
(平成10年に先行で開始された地域もあります)
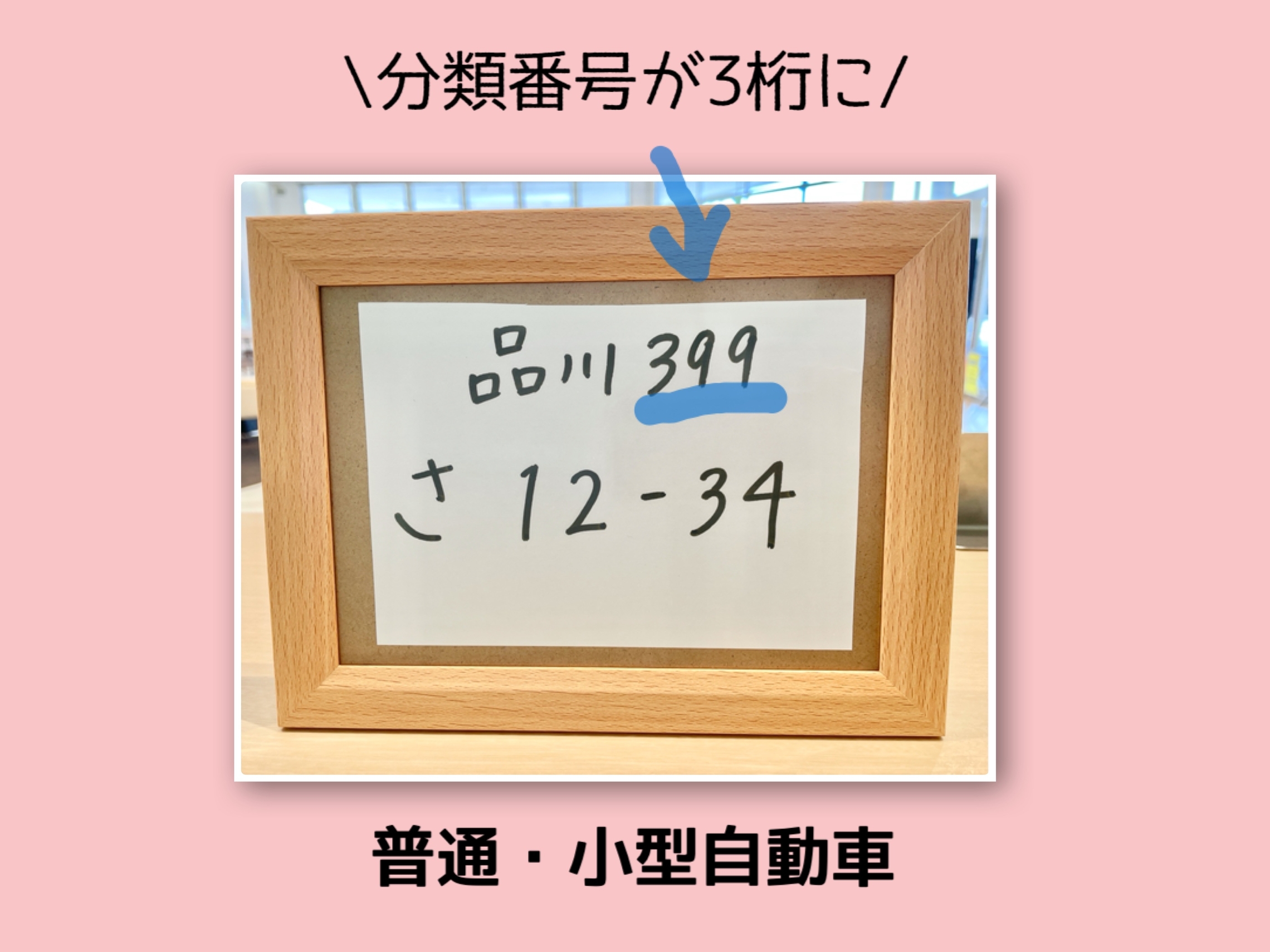
2005年(平成17年)
軽自動車も分類番号が三桁になり、希望番号制もスタートしました。
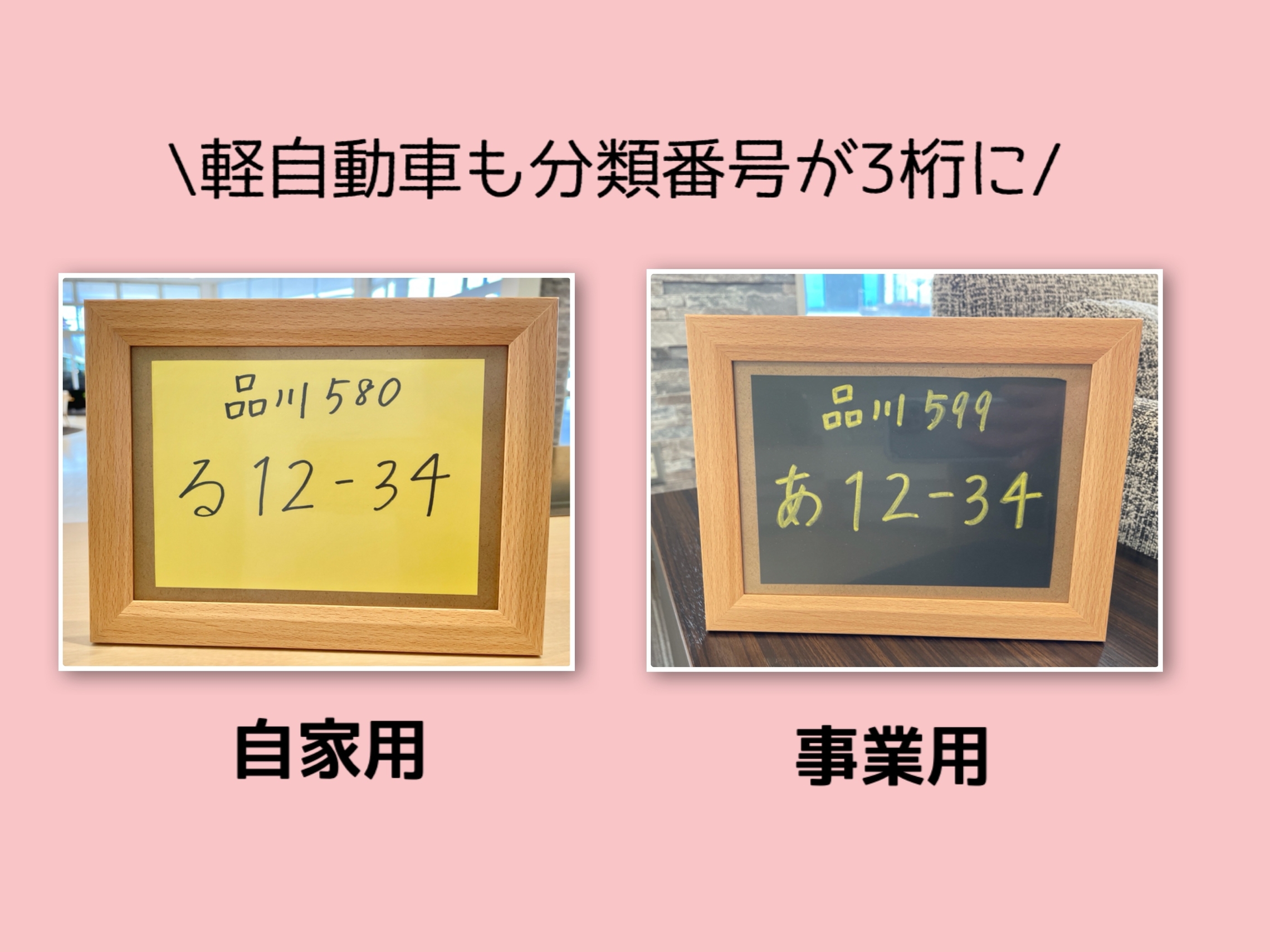
2006年(平成18年)
ご当地ナンバーが導入されました!
平成20年までに19地域20か所で交付開始となりました。
ご当地ナンバーの図柄はこちらから🍊(リンク:国土交通省ホームページ)
いかがでしたか??
ナンバープレートって色も表記も少しずつ変化して今の形になったんですね!💡
意外と歴史が深くて驚きました(; ・`д・´)
これから、すれ違う車のナンバープレートを見てみるのも楽しそうだなと思いました(^^)
皆さんもぜひ注目して見てみてはいかがでしょうか🌟
ナンバープレートを記念保存する方法をご紹介した記事はコチラ↓↓
今治店!!ナンバープレートの記念保存って??
次回のブログは、4月・5月の限定ドリンクについてお知らせしますので、楽しみにしていてくださいね🌸


